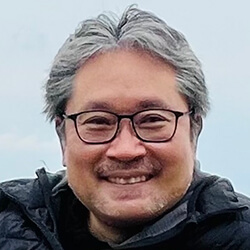講演・パネル
招待講演
第4世代AIと医学生物学データ
2010年代に始まった第3世代AIである深層学習の急激な発展は、わずか10年で次のフェーズに入ったと認識されている。大規模言語モデルで実証された多目的モデルによる第4世代AIである。本講演では第3世代AIと第4世代AIの相違点や「基盤モデル」の定義を明らかにし、医学生物学データをいかに第4世代AIに適合させていくかについて議論したい。
関連資料のリンク
登壇者
- 清田 純
- 理化学研究所 数理創造研究センター・数理展開部門・医科学深層学習チーム チームディレクター 生命医科学研究センター・統合ゲノミクス研究チーム チームディレクター 同・マルチオミクス基盤部門・プロテオーム解析ユニット ユニットリーダー 同・予測医学特別プロジェクト・医療データ深層学習特別チーム チームディレクター 情報統合本部・基盤研究開発部門・医科学データ共有開発ユニット ユニットリーダー
- 経歴:現在、理化学研究所で上記5つの研究室を率いている。1996年に筑波大学医学専門学群を卒業し心臓血管外科の研修医を経て、幹細胞生物学を研究し東京大学で博士(医学)を取得。2006年から2016年までスタンフォード大学で1細胞生物学、システム生物学、データ駆動科学、機械学習を研究。研究テーマは、AIと生物学、医学、さらにその先の分野に及ぶ。他に筑波大学教授、株式会社アバターイン・アドバイザー等。日本ディープラーニング協会有識者会員。

口頭発表
統合化推進プログラムの歩みと今後の課題
講演概要
統合化推進プログラムは、バイオ系データベースの統合を目的に2011年に発足し、以来、国際的にも高い評価を得るに至ったデータベースの構築を支援してきた。2023年からは従来型の支援に加え、次世代を担うデータベースの育成を目的とする支援も開始している。しかし、既に国際的地位を確立したデータベースをいかに持続的に支援してゆくかという課題は、いまだ解決されていない。バイオデータの多様化と高度化によって統合の重要性が増すと同時に、AIの進展によってデータベースを取り巻く状況が劇的に変化しつつある今、統合化推進プログラムの在り方を改めて考えてみたい。
関連資料のリンク
登壇者
- 伊藤 隆司
- NBDC「統合化推進プログラム」 研究総括 / 九州大学 生体防御医学研究所 特任教授

大規模言語モデルを活用した病的スプライシング変異データベースの自律的構築
講演概要
SSCV DBは、Sequence Read Archive等の大規模な公共トランスクリプトームデータを、独自のアルゴリズムで再解析し、同定したスプライスサイト生成変異を格納するデータベースである。
本研究課題では、大規模言語モデルを活用した病的予測アノテーションの追加を行う。さらに、シークエンスレポジトリへの新規データの追加に伴い、自律的に再解析を実行し、データベースを更新する基盤の開発を進める。
関連資料のリンク
登壇者
- 白石 友一
- 国立がん研究センター 研究所 ゲノム解析基盤開発分野 分野長

4Dゲノム状態の理解と可視化を支援するデータベースの構築
講演概要
独自に開発したPHi-C(ファイシー)法を用いて、公共の3次元ゲノム構造データ(Hi-Cデータ)に対し、動的な3次元ゲノム構造(4Dゲノム状態)を網羅的に解析し、その可視化を実現する「PHi-C database」を構築する。GPU計算による高速化と大規模化を進め、複数のHi-Cデータを直感的に比較・理解できる4Dゲノム情報の統合的可視化基盤を提供する。これにより、細胞核内におけるゲノムDNAの動的高次構造の理解を促進し、シミュレーションや理論解析、統合ゲノム解析を通じて新たな仮説の創出と知識発見に貢献することを目指す。
関連資料のリンク
登壇者
- 新海 創也
- 理化学研究所 生命機能科学研究センター 上級研究員

データサイエンティストフレンドリーな毒性病理画像データベースCuratoxiiの開発
講演概要
毒性病理画像は医薬品等の安全性評価にて欠かせない他, 化合物の個体での作用を恣意性なく記述するデータである。
一方, 疾患画像に比してデータベース(DB)の整備が進んでおらず, 当該データを対象とするデータサイエンティストは限られている。
上記課題解決に向け我々は, データサイエンティストフレンドリーな毒性病理画像データベースCuratoxiiの開発に取り組んでいる。
本発表では毒性病理画像解析分野の背景となぜDB開発がその課題解決に資するかを中心に, プロジェクトの概要を紹介する。
関連資料のリンク
登壇者
- 水野 忠快
- 東京大学 大学院薬学系研究科 助教 / 統計数理研究所統計思考院 特任助教

パネルディスカッション
データベースなしじゃ語れない!
~マルチモーダル×AIは科学にどんな変革をもたらすの?~
本パネルディスカッションでは、生命科学におけるマルチモーダルデータおよび AI の活用について取り上げるともに、それに必要となるデータベースのあり方について議論する。急速に発展するAI技術、計測技術およびデータベースが生命研究のスタイルをどう変えて行くのかをそれぞれの専門家を交えて議論し、生命科学とそのための情報基盤(データベース、AI技術、スパコンなど)の将来像を展望する。
関連資料のリンク
オーガナイザー
パネリスト
- 清田 純
- 理化学研究所 数理創造研究センター チームディレクター

- 瀧川 一学
- 東京大学 大学院新領域創成科学研究科 教授 / 北海道大学 化学反応創成研究拠点 特任教授 / 理化学研究所 革新知能統合研究センター チームディレクター